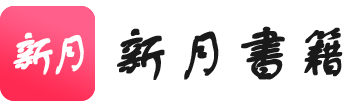日露戦争後、わが陸軍はロシアを仮想敵とし、わが海軍は米国を仮想敵としたことで、陸海軍の対立は必然的に深まり、軍拡競争が生じる。これを憂慮した山縣有朋元帥は、1906年10月に国防政策の確立の必要性を説き、天皇に追悼の意を表した。明治天皇は、元帥に諮問した上で、参謀総長と海軍司令官に国防政策の策定責任を負わせた。
そこで明治49年(1906年)12月20日、両参謀総長が交渉を開始し、わが国の国防政策を策定し、2年目の明治40年(1907年)4月4日に天皇に報告し、承認を得た。国防政策の内容は次のとおりです。
帝国防衛政策
1. 帝国の国防政策の本来の意味は、自衛を目的とし、国の権益を擁護し、建国と進歩の国策を遂行することである。
2. 帝国の国防政策は、帝国の国防の本来の意味に基づき、国力に鑑み、初戦の戦力を可能な限り高め、迅速な決断を下すことを基本とするものである。原則。
3.帝国の国防 帝国の国防の本来の意味から、ロシア、アメリカ、フランスを狙い、東アジアで攻勢に出ることができる軍備を整備する。
4.帝国の国防に必要な軍隊は次のとおりです。
陸軍には、平時は 25 個師団、戦時は 50 個師団があります。
海軍第八艦隊。
この国防政策の目的は、1906 年 1 月に山県元帥によって提示され、最初の架空の敵国はロシア、2 番目は中国 (清王朝)、3 番目はロシアと中国 (清王朝) でした。ロシアとフランス、ロシアとドイツ、ロシアとフランスとドイツの間で同盟を結ぶことも可能です。わが国は1902年に日英同盟条約を結んでいるので、ロシアとの取引しか考えられないと考えています。しかし、海軍との協議の結果、ロシア、アメリカ、フランスが仮想敵国になることが合意されました。
国防方針によると、陸海軍の兵力の運用方法を明確にした「兵力運用要領」は、おおむね次のとおりです。
帝国軍の計画
1. 帝国軍の戦闘においては、国防方針に従い、陸海軍の緊密な連携の下、最初から攻勢に出る。防御戦は、最後の手段としてのみ使用するように制限されています。そのために陸軍と海軍は、敵の野戦軍と主力艦隊を速やかに撃破し、必要な地域を占領しなければならない。
2. 陸軍の対露戦争の要点は、常に好機をとらえ、韓国を基地として、主戦場を中国吉林省北東部の韓国咸鏡路と中国吉林省沿岸部に導くことである。ロシア南部。海軍作戦は、極東の敵艦隊を迅速に殲滅し、極東のロシア沿岸を制圧し、同時に軍の海上輸送を確保する必要がある.必要に応じて、台湾海峡とバシー海峡(台湾と台湾の間)を警備する.フィリピン)とスタンバイ状態を維持します。
3. 対米戦争では、開戦時、まず東太平洋の敵海上戦力を殲滅し、西太平洋を制圧し、帝国の通信回線を確保し、防御作戦で撃破する我が近海で海を渡る敵の艦隊を攻撃し、敵の戦意を弱めるために長期不敗の戦略態勢を維持する。
この兵力計画に基づき、陸海軍司令部は毎年、「年間戦闘計画案作成要領」を協議・策定し、これに基づいて陸海軍の「年間戦闘計画」を協議・策定する。
ここで注目に値するのは、日露開戦直後の 1904 年 4 月、米国は、当時の陸軍参謀総長チャフィー将軍の提案に基づいて、日本に対する「オレンジ プラン」戦闘計画の策定を開始したことです。陸軍参謀 戦闘計画が作成されました。日露戦争の終結から 2 年後の 1906 年、セオドア・ルーズベルト大統領は、米国艦隊を東太平洋にできるだけ早く派遣する方法を検討するよう軍に命じました。
1907 年 4 月、日本海軍は「国防方針」に従い、米国を仮想敵国と見なし、侵攻する米国艦隊を我が国近海で迎撃し、殲滅することを決定しました。
この点で、米国は日米戦争の準備において日本より約 3 年先行していた。